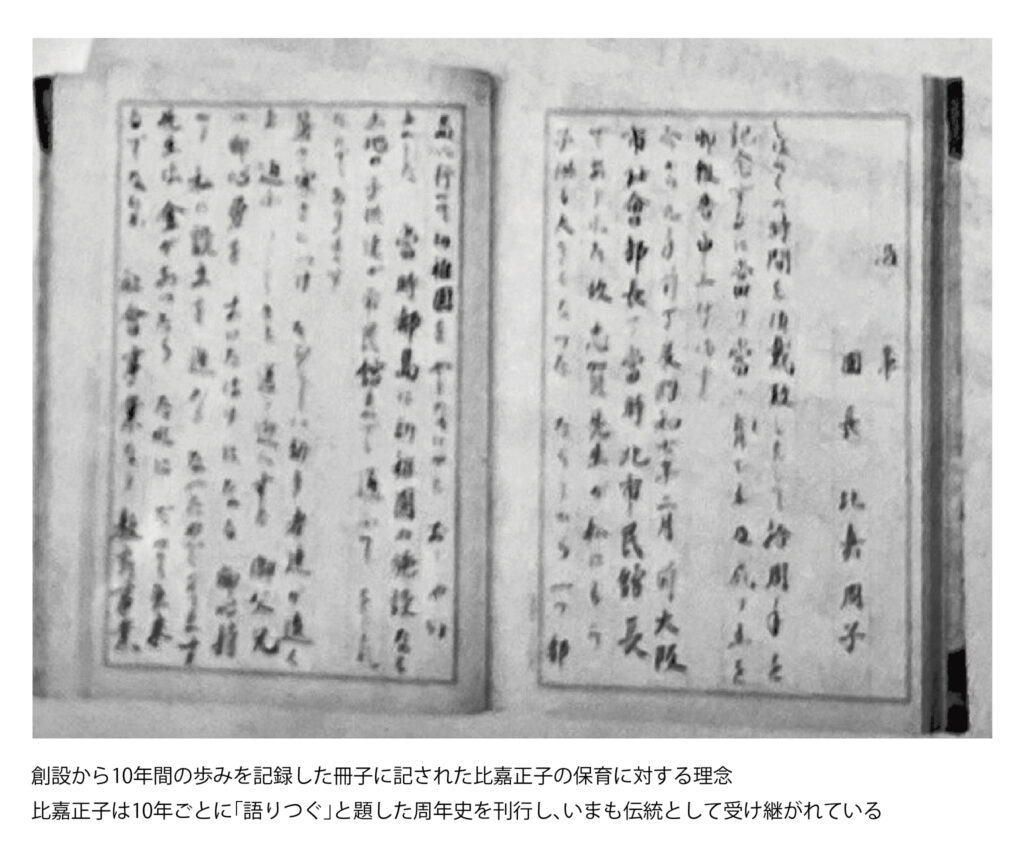第17話 我が子たち
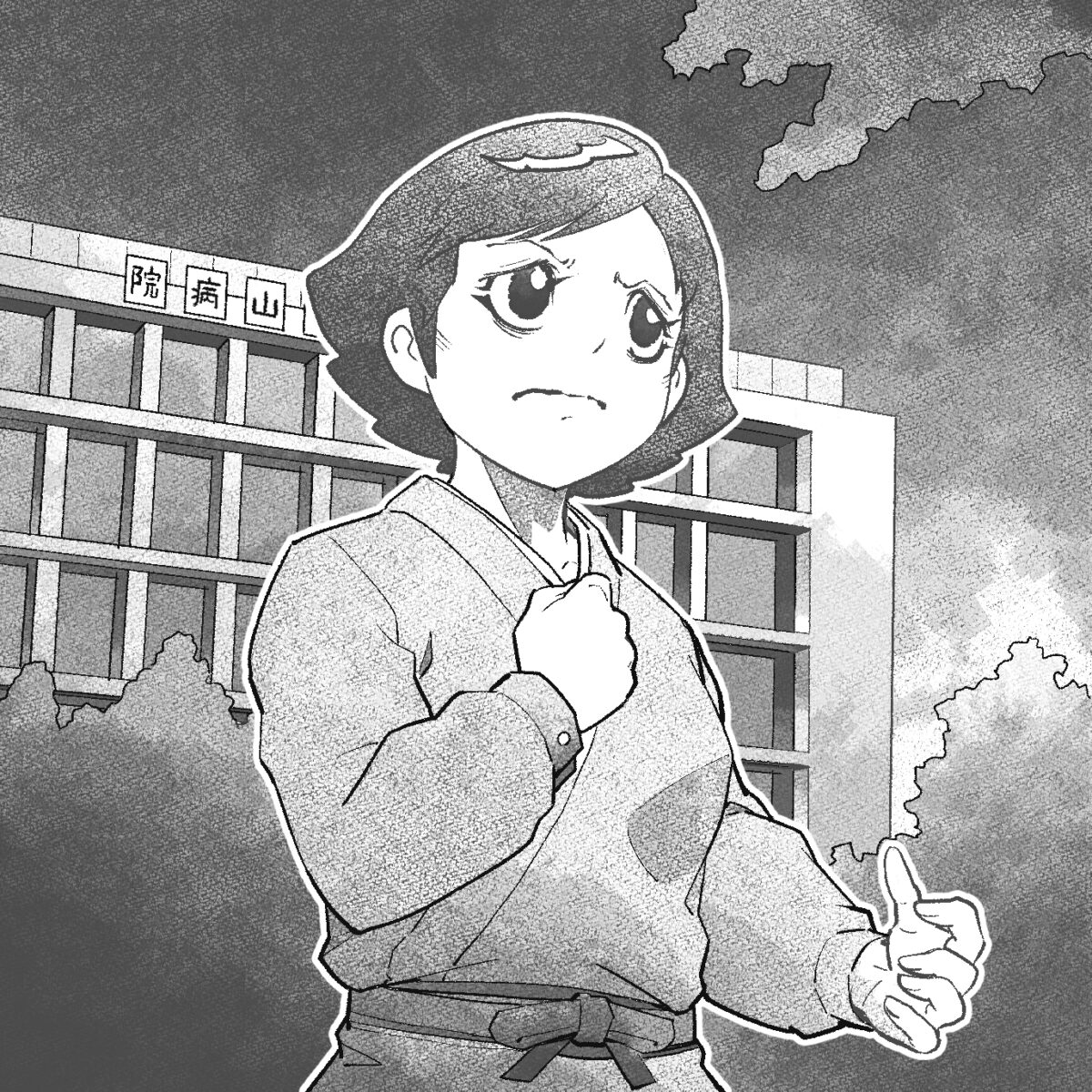
1941(昭和16)年3月、「私立都島幼稚園」は創立十周年を迎えた。その年の12月8日、日本は米英に宣戦布告し、太平洋戦争へと向かい、都島幼稚園を取り巻く環境に変化が見えはじめた。そして正子の私生活にも多くの出来事があった。
北都学園創設時、長女は四歳、次女は二歳、そして末っ子の長男は生後間もない乳飲み子だった。正子は三人の幼子がいる家庭を守りながら、十年間で八百人の園児へも、我が子に等しい愛情を注ぎ続けてきた。園児たちの中に混ざって育ってきた子ども三人は、そんな母の姿を見て、正子が胸に抱く大きな使命の中で育っていった。正子はよく家の事もした。いつも仕事を終えた少し遅い夕刻、買い物客がひいたころの八百屋に行き、店にあるものを買って帰って、材料に合わせて料理を作った。手早くできるチャーハンは食卓の定番で、夫婦の生まれ故郷の沖縄料理もよく作った。
正子のよき理解者であり支えである賀盛との時間は、なくてはならないものだった。帝国銀行に勤め、小林一三(こばやしいちぞう)に将来を期待されるほどの思慮と才のある賀盛だった。興味深い本があれば、「読んでごらん」と勧めるような柔らかな方法で、正子の見聞を広めてくれた。本名比嘉周子に戻る家庭は、正子にとって、かけがえのない居場所であった。ただ、その家庭においても、時間との追いかけっこはやまなかった。
次女ルイズの入園式の朝のことだった。一緒に連れて出ようとしたら、ルイズは裸足にゴム靴を履いて、庭伝いに一人で園庭に入ろうとしていた。正子は慌てて娘の手を引っぱって家に連れ戻り、靴下を履かせた。いつもどおり母親の手を煩わせずに一人で園に行こうとしていたルイズは、きょとんとした顔で、靴下を履かせる母親の姿を見ていた。入園式、修了式といえば園児たちの大切な日。子どもたちにとってよい日となるように心を配ってきたというのに、我が子がその日に、靴下も履かずにいることすら見過ごすところだった。入園からしばらくして、そのルイズが、薄い紙で作ったバラの花を大切そうに持っていた。先生がルイズのために作ってくれたらしい。それまで、自分のためだけに何かをしてもらうということがなかったルイズは、両手にのせたそのバラを、とても嬉しそうに眺めていた。
かまう時間がなかったのは三人のどの子に対しても同じだった。だが長女、次女、長男の三人の真ん中のルイズは、傍目に不憫に見えたのかもしれない。近所の、泉という家の夫婦がこの娘を可愛がった。青空保育園を「私立都島幼稚園」に発展させ、福祉的幼稚園という他に類のない保育システムをつくってきた、この数年間。正子の毎日は、文字通り時間が矢のように飛んでいった。そんな正子には、しばしば次女の面倒を見てくれる泉の家がありがたかった。蝶よ花よと可愛がってくれる泉の家を、ルイズも気に入っているようで、機嫌のよい娘の姿にホッとした。そんな正子の様子に、泉夫妻の中に一つの思いが生まれた。ある日、泉夫妻から、「自分たちがルイズをひきとりたい」という申し出があった。
泉夫妻には感謝していた。しかし、充分にかまってやれない娘の面倒を見てもらって有り難いことと、養女に出すことは話しが別だ。泉夫妻から養女の話を切り出されて、正子と夫賀盛は思案に暮れた。入園式の日の身支度にすら手が回らなかった自分の手もとにいることと、世間並み以上に可愛がってくれる泉の家で育つことと。どちらがルイズの幸せなのか、思いあぐねた。
「おじちゃん、おはよう」
前の晩、泉の家に泊まり、保育園に行く支度をしに帰ってきたルイズが、顔を洗っている父親に向かってそう言った。我が子の言葉に耳を疑い立ちすくむ父親を残して、ルイズは機嫌よく、いつもどおり庭伝いに園庭に入ると、園舎に向かってスタスタと歩いていった。
夜、子どもたちが寝た後、その朝のことを賀盛から聞かされた正子も言葉を失った。「今まで育ててきた娘におじちゃんと言われた」と、温厚な夫が珍しく憤慨している。その姿が、薄い膜一枚を通した向こうの景色のようだった。
ルイズが無意識に口にした言葉に、我が娘の心の深淵にある寂しさを垣間みたようだった。それから少しして賀盛と正子は、ルイズを泉家に養女に出すことを承諾した。工場を出すために大阪に来ていた泉夫妻は、里心がついてはいけないとルイズを養女にすると、工場を人に任せてすぐに東京に戻った。家でも保育園でも、次女ルイズの姿を見ることはなくなった。手が回らず放ったらかしのようだったが、姿が見えなくなって、無意識にその姿を追い、様子を確かめていたことを、あらためて思い知った。
正子に、一人の母親としての寂しさ切なさに心をまかせる有余など与えられなかった。年々増加する入園希望児に応じて園舎、園庭、設備の拡充を図らなければならなかった。また刻一刻と濃くなっていく戦況の中でも、園児たちをのびのびと守り育て続ける責務があった。
1942(昭和17)年、女学校三年生の長女牧子が、結核で長期入院することになった。父親賀盛に似てふくよかな輪郭の顔で、いつも物静かにニコニコとしている牧子は、勉学を好み優れていた。音楽の先生からは音楽家に、国語の先生からは文学者に、算数の先生からは数学者になってはどうかと勧められた。そんな牧子が、一日も早く学校に戻れることを正子は願った。長女牧子の入院から程なくして、国民学校六年生の長男健が、腹膜炎に罹り入院した。正子に似て活発でやんちゃな健が病に伏すなど、思ってもみないことだった。
それまで病気らしい病気をしてこなかった牧子と健の入院。何をおいても二人の傍にいてやりたかったが、正子には園長としての務めがあった。一日たりとも仕事を休むことなく、一度たりとも遅刻することもなかった。そして戦況の悪化に伴い、防警団や隣組など地域防災の負担も大きくなっていった。正子は都島の女子青年団長の重責を負い、週に一度は看護婦として立つ訓練と、闘いの訓練も行なった。「私心を捨てて大儀につく」ことが当然で、家庭の都合で義務を怠るなど許す世の中ではなかった。
仕事前の早朝と仕事を終えた夜に入院中の二人を見舞った。少しでも栄養をと、夫婦の食事を削って牧子と健に運んだが、もとから少ない配給食からでは、育ち盛りの二人の滋養にはとうてい足りるものではなかった。薬に不自由し、栄養分もなく、治療のままならぬ我が子を見ているしかない歯痒さ、心許なさ。そして比嘉周子という母親と、比嘉正子という職業人との板ばさみ。片時も離れず我が子の傍に居てやりたいと願う母親の情と、自分を頼りにしている園児たちやその母親父親たちへの思い。我が子と園児たち双方の生命を守る。その無理と矛盾に耐え続けるために、神経が剃刀の刃のようになり、肉体は痩せ衰えていった。ただただ気概だけで生きているような毎日で、ふいと気がぬけたときなど、何もないところで躓いたりよろけたりすることもあった。初めから長期入院と告げられていた牧子だけでなく、健の入院も長引いた。母親と園長、二重の生活を続けるには限界があった。
「我が子がどうなろうと、園児たちを守ることが取るべき道だ」それが正子の選択だった。
十八歳のとき、正子は洗礼を受けている。だがそれは、「洗礼を受ければ、学費も寄宿舎費も不要で、神学校で学ぶことができたから」と、照れ隠しもあってか、そう話すこともあった。神学校で出会った宣教師、伝道師たちの敬虔な姿に、「私はクリスチャンです」などと口にすることはくちはばったく、めったになかった。しかし何か重大な、自分一人の力ではどうにもならない難題に直面したとき、一心に神に祈っている自分があった。正しいと信じる道を無心のなかに求めた。
そしてこのとき、我が子二人だけでなく、正子を必要とする多くの子たちのために生きることが、その道だった。
正子の覚悟は決まった。