
第25話 社会づくりへの前進
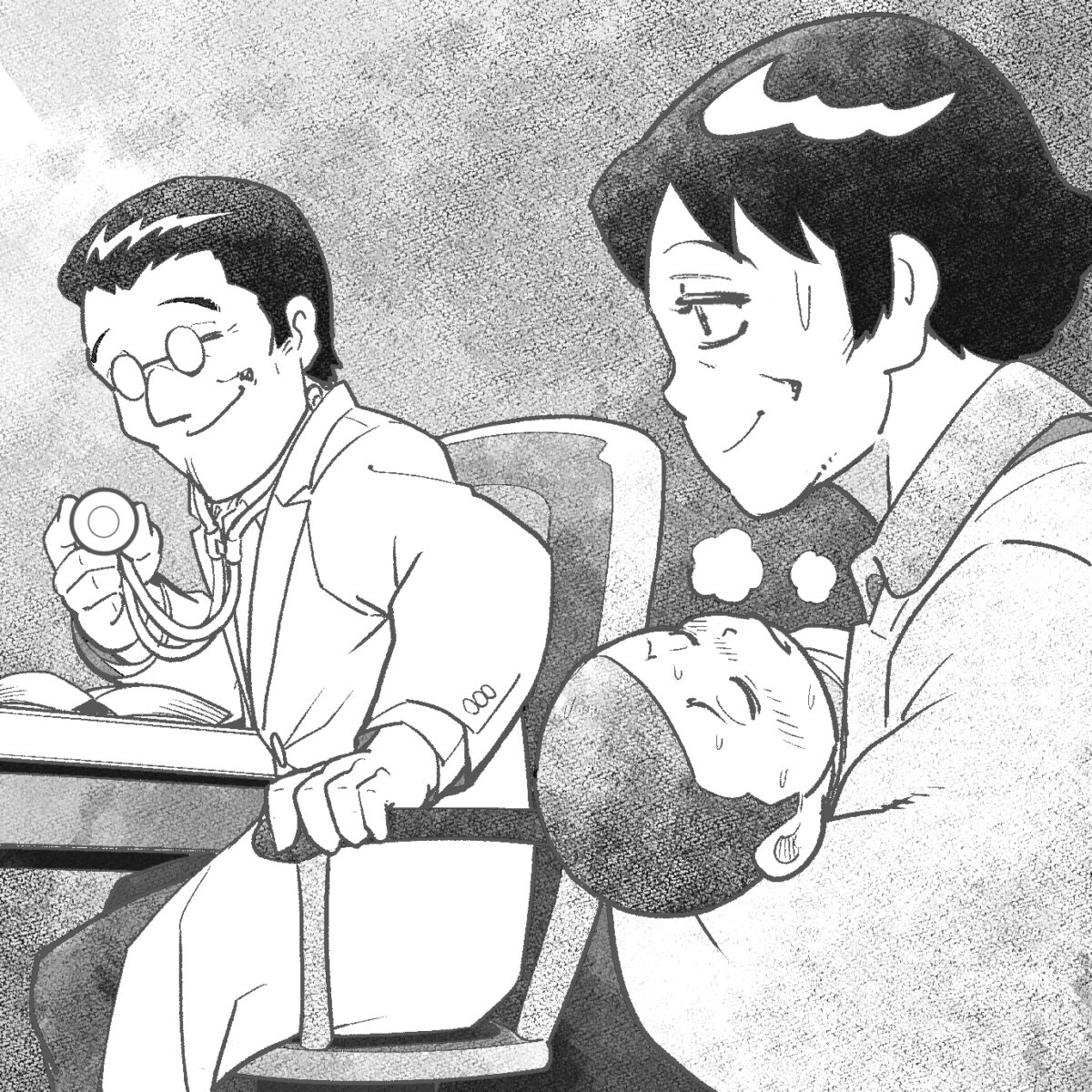
1951(昭和26)年、正子は財団法人 都島友の会の事業の一つとして、都島診療所を開設した。認可を受けた事業内容の「社会事業法による医療保護」の実施だった。
◇
都島保育所を開いて間もないある日、保育中に一人の幼児が高熱を出した。急いで親に連絡したが仕事中で連絡がつかないまま時間が経った。当時、都島区に保健所はなく、近隣に病院もなかった。安静にさせて水で冷やして応急処置をするしかなかった。正子は胃の痛くなる思いで園児を看た。それからも、園児たちの急な発熱は続いた。その度に親への急報を試みたが、母子家庭や両親共働きの家庭ばかりで、園で応急処置をほどこすしかないのが現実だった。
子どもの生命を守ることは何をおいてもなすべきことだった。我が子二人を亡くしている正子は、子を失う親の痛みを嫌というほど知っている。子どもを預けた親たちが安心して働けるように、園で子どもたちの健康管理を引き受けようと決めた。引き受ける限りは半端なことはしない。近くに医院ができそうもないのなら、法人で診療所を開設してはどうかと考えはじめたところに、知己の医師夫妻が正子のもとを訪ねてきた。正子と同姓の比嘉といった。比嘉医師夫妻も、そろそろ疎開先から町に戻りたいということで、子どものことや住居のことなどの相談だった。夫妻揃って、医療技術に優れていることは知っていた。正子の夫賀盛とも教会で交流があり、ヒューマニズムを重んずる人間性に触れていた。医師として人として信頼できる医師夫妻の来訪は、またとないタイミングだった。
正子は診療所の開設を決断し、準備を進めた。とはいえ、園の再建に用立てた資金はもう残っていない。けれど、子どもたちを守るために必要ならば、何としてでも実現する。それしか考えなかった。そんな正子の使命感は賛同者に恵まれた。まだ焼け野原のままだったが土地を提供してくれた地主、建築資金を貸してくれた婦人、そして寄付をしてくれた人たち。地域の賛同者たちの協力を得て、都島児童館の近くに、財団法人都島診療所ができた。
1951(昭和26)年8月、比嘉夫妻を医師に迎えて、診療を開始した。小児科、内科、外科、婦人科の診療を行い、都島児童館の園児の健康管理に加えて、地域の人たちの受診も受け入れた。
患者の身になって、患者の都合の良いときに治療が受けられることを診療方針にしていた都島診療所の受診者は、開設早々から増加の一途だった。その状況に診療所を少し増築しておいた方がいいのではないかと正子は、比嘉医師に相談した。すると「今、小規模の増築をするよりも、土地の拡張をしておいた方が将来の発展のために役立つ」という意見が返ってきた。正子はその提言を受け入れ、診療所裏の空き地三百坪を購入した。
1952(昭和27)年、都島友の会は財団法人から社会福祉法人へと組織を変更した。正子は、それによって都島診療所も地域医療への役割が大きくなると判断。購入してあった土地に病棟を建て増してベッド数を増やした。そして1954(昭和29)年、都島診療所は都島病院に昇格することになる。
都島病院は、診療対象を地域の生活保護者、健康保険適用者、労災適用者、自費患者と広げ、地域医療の担い手としての性格を明確にした。保育を軸に、地域社会づくりを行う。社会事業への復帰に加えて、新たにした決意。その決意への前進だった。
◇
都島児童館が完成し、社会をつくる仕事をしたい。女学生時代に芽生えた夢に向かって突き進んでいたころ、正子の前にもう一本の道が現れた。それは都島の地に戻ると決めたときに幕を引いた婦人運動の道。戦後の食糧難、命を脅かす食糧危機を打開せんと立ち上がった生活を守る闘いの道だった。
疎開先の鴻池で終戦を迎えた正子は、おかみさんたちによる生活の闘いを展開する「主婦の会」を、リーダーとして引っ張ってきた。その後、子どもたちが待つ都島の地に戻ってくるにあたって、主婦の会を脱会してきた。保育園の再建と婦人活動のリーダーの兼務は、いかにバイタリティー溢れる正子でも荷が重すぎた。何事にも全力で打ち込む。それが比嘉正子だった。
都島児童館の建物が完成すると、鴻池のおかみさんたちや、正子に続いて主婦の会を脱会していたおかみさんたちが、開園準備の手伝いにきてくれた。隣接するとはいえ市境を越えて日参してくれる仲間たちの気もちが嬉しかった。家族を、子どもたちを飢えから守るために共に闘った仲間たち。心強い応援を得て、開園準備に拍車をかける日々だった。
主婦の会での泣き笑いの思い出話に花を咲かせながら、ポスターや飾り付けづくりに勤しんでいると、脱会したおかみさんの一人がぽつりと言った。
「比嘉さん、建物も完成したし、そろそろ婦人運動にもどってらっしゃいな」
それをきっかけに、口々に正子を口説きはじめた。
「私たちがそれぞれの地域で活動していても、小さな力で終わってしまう。小さな力を大きな力にできるような組織づくりに、比嘉さんの力がいるの」
鴻池のおかみさんたちも、口説きこそしなかったが、気もちは同じだという顔で正子を見ていた。
皆の熱意はありがたかったが、「何を言ってるの、関係者の皆さんにも引退のご挨拶をしたっていうのに。そんなみっともない。今は保育園の再開でてんてこまい。そんなこと考えられませんよ」と、正子はきっぱり断わった。
皆、ほんとうに残念そうな様子だったが、執拗には言わなかった。そしてそれからも、変わらず手伝いにきてくれた。保育を軸にした社会づくりという夢への応援が心強かった。社会事業と婦人運動、正子の中では根が一つの二本の幹。その二本の幹が一緒になって、子どもたちの館づくり、そこから始まる地域づくり、社会づくりに向かっている。
和気あいあいと、泣き笑いの思い出話から、これからの世の中のことについて話をしているうちに、正子の中に生活を守る闘いへの思いが甦ってきた。台所に根づいた、生活者による生活を守る闘い。それは子どもたちを守る闘いだった。子どもたちへ手渡す社会をつくる仕事だった。語り合っていれば、皆の胸の内にある正子の復帰への熱望が伝わってくる。正子は顧問として連合組織を助ける約束をした。1949(昭和24)年の暮れだった。
役員はもちろん会員にもならない外部の顧問という条件付きだったが、その場の皆は跳び上がる勢いで喜んだ。早速、連合組織発足を待ち望む会員を集め準備にかかった。準備のための会合はいつも都島児童館で開かれた。正子の社会事業と婦人運動の距離が物理的にも近くなった。
社会の坩堝の中で理想を実現すると情熱に燃えた二十歳過ぎのころ。社会の環境を変えなければ、一施設にできることには限界があると叩きのめされた現実の苛烈さ。いま、保育施設という拠点に、生活者の立場から生活を守る仲間たちが集まっている。都島児童館を集合拠点に広域で手を繋ぐ「関西主婦連合会(関西主婦連)」が誕生した。鴻池での主婦の会を立ち上げた盟友、岩崎ウタが都島支部のリーダーとして参加していた。
「子どもは国の宝だよ」正子は口癖のようにそう言った。子どもたちを守ることは社会の未来を、国の未来を守っていくことだ。今の子どもたちを守る社会、そして次世代の子どもたちに手渡す社会。それをつくることこそ正子が情熱を傾けるすべてだ。
正子を顧問に立ち上がった関西主婦連は、〈衣食住部〉〈政治経済部〉〈教育部〉という組織の三本柱を立てた。生活を守り、社会の将来の担い手を育て、その実現のために政治経済という大きな環境を整えていくという考えが、基盤になった組織づくりだ。
1950(昭和25)年暮れ、外部顧問とし関わってきた正子が、関西主婦連合会の会長に選ばれた。満場一致の選出だった。保育を軸にした社会事業と婦人運動。同じ根から育った二本の幹が、正子を真ん中にかたく結びついた。都島友の会の母の会と、おかみさんたちの関西主婦連。保育を軸に地域社会をつくっていく。地域社会が広く手を繋ぎ、大きな環境を整えていく。そして次世代、その次の世代の子どもたちに、よい社会を遺していく。正子の思い描く社会づくりへの、新たな扉を開けた。